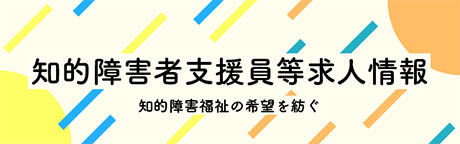事業計画
2024(令和6)年度 京都知的障害者福祉施設協議会 事業計画
長かったコロナ禍も一段落をし、社会活動も活性化の兆しが見えてきました。ターニングポイントにある障害者福祉において、この失われた4年間はあまりにも大きなものでしたが、全員が一丸となり活発な活動を行っていきたいと考えています。会員各位のご協力の程、よろしくお願い致します。
組織の充実
- 非会員事業者に声掛けし、協議会に参画をいただくよう努力します。
- 全員が何らかの委員会、部会の構成員となり、行事に参加いただく体制を取ります。
他の組織との連携
- 京都府、京都市との政策協議の充実を図り、実りの多いものとします。
- 日本知的障害者福祉協会、近畿地区知的障害者施設協会の行事に積極的な参加を図ります。
- 近隣の団体(北陸地区協会)の地震支援を継続していきます。
委員会・部会の充実
- それぞれの委員会・部会員の名簿作成を行い、全員で活動を行っていく体制を整えます。
- 行事・文化部会は今年度もコンサートを開催します。ついては、体制を整え、一人当たりの負担軽減を図ります。
- 研修部会においてはタイムリーなテーマで研修頻度の増加を図ります。担当責任者を決め、負担の集中する事がなく、持続していける体制を取ります。
事務局体制の充実
- 5月に京都社会福祉会館に移転します。
- 業務がスムーズに流れ、会員の皆様に協議会活動に参画いただき易い体制を整えます。
政策委員会
- 重点課題
今年度は、京都市との予算要望政策懇談会を、着実に開催したい。2023年度は近畿地区知的障害者施設関係職員研修会を開催したが、その開会に京都市からは出席が得られなかった。市会の開催中で予定が立たないとのことであったが、京都府からは出席もあり、平素からの関係づくりが希薄になっているのではないかという反省があった。以前は毎年度、予算要望書の提出と政策懇談会を実施できていたが、今年度はこの予定を立てていく。
京都府とも、同様に懇談会の設定が望ましい。今年度は報酬改定のあった年度でもあり、各法人・事業所の運営状況に影響が出ていないか気になるところである。
政策委員会としては、各事業所にアンケートをお願いし、運営への影響の有無についてまとめた上で予算要望政策懇談会に臨みたい。アンケートについては、メールで依頼する。
- 事業実施計画
- アンケートの実施
2024年5月13日 京都知福総会にて会員名簿及び連絡先メールの把握
6月上旬 アンケート依頼開始 7月上旬 アンケート結果集計 - 政策委員会の開催
2024年7月22日第1回政策委員会- 施策の動向、課題の共有
- 報酬改定影響状況調査アンケート結果について
- 京都府、京都市への予算要望書の作成について
- 今年度の日程
7月末
京都府施設協、京都市施連協の共通要望書提出締め切り
10月頃
京都府との予算要望懇談会
京都市との予算要望懇談会(10/1 14:00〜、場所は未定)
- アンケートの実施
- 必要予算(概算)
50,000円
- 重点課題
令和6年度の報酬改定における主な内容についても触れられているが、障がい者の意思決定支援を推進する方策について、配慮して適切な支援内容が求められている。そこで今年度研修のテーマを「意思決定支援」とし、連携できる種別部会と一緒に研修会を開催して、利用者の地域生活への移行や日中活動利用の意向調査、個別支援会議やサービス担当者会議などへの本人参加など、事業所として求められる支援についての確認と実践報告や情報交換を行うべく、研修の機会を設けて意識向上をはかる。
虐待防止措置・身体拘束の適正化についても、引き続き各施設での研修や対策が求められるところである。継続して人権倫理委員会と協力してより良い支援につながる研修会や情報共有の機会となる研修会を企画する。
- 事業実施計画
- 京都知的障害者福祉施設協議会の種別部会と連携し、情報交換につながる研修会を開催する。
- 知的障害者福祉施設・身体障害者福祉施設等職員研修会の開催。
(京都府社会福祉協議会・京都府障害者厚生施設協議会・京都知的障害者福祉施設協議会) - 「より良い支援」につながる内容で、人権倫理委員会と共催の研修会を開催する。
- 必要予算(概算)
300,000円
人権倫理委員
- 重点課題
- 福祉施設現場における人権侵害、虐待事案は、現在においても報道が全国に後を絶たない状況が続いている。京都知福協においても、施設長をはじめ現場職員を揚げて、この問題に関心を向け、「より良い支援」に結びつくよう積極的な取り組みが求められている。信頼される障害者福祉施設・団体となるべく実践を積み重ねていく必要がある。情報交換の場の設定、研修、情報発信の3つを軸に進めていく。
- 委員会としての機能強化のため、委員の増員を図る。
- 事業実施計画
- 権利擁護向上に向けた情報交換座談会の実施(集合形式)
- 2023年度に実施した法人・事業所における権利擁護・虐待防止研修実施に関する実態調査結果の情報発信(情報提供)
- 地域支援部会主催のスキルアップセミナーヘの実施協力
- 研修委員会との共催研修の開催
- 事業所における支援改善例や実践事例を学ぶ見学会の開催
- 会員施設において虐待事案が発生した場合、会長、副会長に対応をお願いする。委員会として、虐待事案についての実態把握を行い、人権や権利擁護意識の向上に向けた意識の共有を図る。
- 必要予算(概算)
350,000円
行事文化部
- 重点課題
事業所の利用者に喜ばれる行事を通して、文化的に豊かな時間を提供します。
- 事業実施計画
昨年度と同様に3箇所の会場にて、「コンサートの集い」を開催します。
令和6年11月27日(水)京都府中丹文化会館(綾部市)
令和6年12月18日(水)文化パルク城陽(城陽市)
令和7年2月中旬頃 京都コンサートホール(予定) - 必要予算
3,300,000円
広報部会
- 重点課題
- 編集方針
手に取り、読みやすい広報誌となるよう内容の精査
協議会内部への情報発信はもとより外部への情報発信ツールとする - 会員施設との連携
Spotlight、商品紹介特集ページなどの情報提供を依頼
- 編集方針
- 事業実施計画
- 京都知的障害者福祉施設協議会機関誌「K.Cニュース」発行(第 212〜213 号)発行に係る会議予定
212号 7月 編集会議 9月 校正会議 11月 発行
213号 12月 編集会議 2月 校正会議 3月 発行 - データ管理
クラウド上でのデータ管理を継続実施し、スムーズな編集作業に繋げる
- 広報誌の記事の検討
利用者ご本人に焦点を当てた「Spotlight」の継続掲載
特集ページ(商品紹介)の充実
施設訪問記事の掲載 - 会議(編集・構成)の実施 形態
WEB/対面を併用した会議形態の検討。
部会員間の情報共有のためのツールの模索と導入。
*編集に係るデータの保存・管理方法の見直し。
- 京都知的障害者福祉施設協議会機関誌「K.Cニュース」発行(第 212〜213 号)発行に係る会議予定
- 必要予算(概算)
600,000 円(K.Cニュース 212号、213号編集・印刷・発送費用)
児童発達支援部会
- 重点課題
- 報酬改定を受けて、各会員施設が適切に対応出来るよう、情報共有・交換を行うとともに、必要に応じて研修を企画。
- 児童福祉事業所の現状・課題を整理。京都府・京都市など行政機関ヘの改善要望に繋げる。
- 事業実施計画
- 児童発達支援部会(対面形式)の開催(年2回程度)
- 管理者等を対象とした研修会の開催
- 「幼児のつどい」については、実施方法を見直すこととし、今後については各会員施設のニーズ等を確認し、検討する。
- 必要予算
100,000 円
障害者支援施設部会
- 重点課題
- 障害者支援施設として、共通する課題や取り組みについて、情報共有や情報交換ができるネットワークの構築に向け、会議や研修などを実施する。
- 他部会との共同活動
- 事業実施計画
- 管理者向け研修会
- 専門職の情報共有、情報交換会
- 必要予算(概算)
50,000 円
日中活動支援部会
- 重点課題
- 事業所間の情報共有・情報交換のため、顔の見える関係作りを行う
- 部会の定例化に向けた検討を行う
- 事業実施計画
- 部会員名簿を作成し、ネットワークを再構築する
- 小規模研修会の開催
- 生産活動・就労支援部会との連携による事業所見学会の実施
- 必要予算(概算)
50,000 円
生産活動・就労支援援部会
- 重点課題
- 工賃向上に向けての取り組み。
- 加盟施設の皆様に参加メリットを感じていただけ参加率が上がるような魅力的な企画。
(施設見学会もしくは研修会)
- 事業実施計画
工賃向上に向けた研修及び、施設見学会の実施。 - 必要予算(概算)
50,000 円
地域支援部会
- 重点課題
障害のある方の暮らしの場が多様化する中、今では施設入所者を上回る方が全国のグループホームにて過ごされています。地域での暮らしには、グループホーム利用が優位にあるのは間違いありませんが、他方で、ヘルパー制度を使いながら一人暮らしやシェアハウス暮らしをされている方もあります。
増え続けるグループホームの質を維持向上し、ヘルパーなど利用できる制度の充実を図ることがご利用者の暮らしを守る上では重要です。事業所同士の顔の見える関係性を樹立し、情報共有を行うこと、支援に携わるスタッフのスキルアップを重点事項として取り組んでまいります。
- 事業実施計画
- 地域支援部会の開催
- 職員研修会の開催
- 全国、近畿等広域の事業所を対象とした研修会等への参加促進
- 近畿地区知的障害者施設協会地域支援部会への参画
- 部会所属事業所同士の連絡ツールの整備、オンラインの体制強化
- 必要予算
60,000 円
相談支援部会
- 重点課題
- 定例部会の開催【2ケ月に一回】
- テーマを決めた研修会の開催
- 児童の部
- 成人の部
- 近畿地区相談支援部会との交流
- 合同の部会(事例検討)
- 研修会の実施
- 京都府社会福祉協議会との連携
- 成年後見制度や府社協による「法人後見」の研修と活用方法の検討
- 事業実施計画
上記の課題と事業計画を新体制のもとで、具体的な日程と内容を詰めていく。
部会の「テーマを決めた事例検討」は成人・児童の事例検討に追加して、成年後見・権利擁護・意思決定支援の事例や課題について検討するグループを作りました。
近畿知福協では、11月に講演会+事例検討のグループワークをする予定で日程調整をしています。
- 必要予算
150,000 円
支援スタッフ委員会
- 重点課題
- 意思決定支援
以前の年度等に実施したアンケートおよび懇談会の結果をもとに委員会を開催。
懇談や情報交換を行いながら研修等に活用できるよう検討していく。
施設間交流も行い、支援者同士のつながりも深めていきたい。 - 成年後見制度
学びの機会や場面を相談支援部会等と協議し、実施する。
- 意思決定支援
- 事業実施計画
- 意思決定支援は知的にしょうがいのある方にとって必須の支援及び考え方である。支援者は難しくとらえすぎることなく、ご本人が自分自身でご自身の生活を選び取って頂けるよう、未経験な事柄をいかに経験、体験していただくか。支援者協同の中で学んでいきたい。
→ 支援スタッフの会議および懇談・研修会を実施し、学びを深めたい。 -
成年後見制度の有効活用においては成年後見人となる人と日常の支援を行う支援者との連携と情報交換が欠かせない。ご本人の意思や思いをいかに根拠をもって類推し、妥当な判断をしていくか。無理なく連携できるシステムについて色々な支援者の意見を聞きながら、提言を整理していきたい。
→ 相談支援部会と連携し、情報交換・意見交換を行いたい
- 意思決定支援は知的にしょうがいのある方にとって必須の支援及び考え方である。支援者は難しくとらえすぎることなく、ご本人が自分自身でご自身の生活を選び取って頂けるよう、未経験な事柄をいかに経験、体験していただくか。支援者協同の中で学んでいきたい。
- 必要予算
40,000 円
2018(平成30)年度 京都知的障害者福祉施設協議会事業計画
日本の障がい福祉は、2003年の支援費制度の導入以来、大きく変わることになりました。障がいのある人もない人も誰もが地域の中で安心して暮らせる仕組みづくりに大きく政策転換が図られてきました。何よりも急速な少子高齢化、団塊世代の2025年問題という人口構造や社会経済状況を背景に、今後利用者の重度・高齢化や訪問系サービスに対するニーズの一層の増加が見込まれます。
今回発表された平成30年度の報酬改定の内容には、こうした課題に対して今後の施設の方向性を読み取る事ができます。特に重度者に対する加算の強化・65歳問題をふまえた共生型サービス拠点の必要。地域生活拠点の機能強化と加算の新設。又、児も含め、各事業所のサービス提供時間の精査。就労分野では、移行実績に加え定着実績に応じた評価。B型の平均工賃別報酬等。支援実績がより重視され、費用対効果が強く打ち出されたものになっています。今回の改定は前述した社会経済状況の中で、より現実的な路線に国が大きく舵をきったものと言えます。こうした施策のあり方については、議論の分かれるところですが、私たち施設事業者も従事者もコスト意識をもち、提供する支援のあり方を不断に見直し、質を高めていく努力が社会の公器としての私たちの責任であり、当協議会の使命ではないかと思います。
2018年度重点活動
- 2018年度報酬改定影響調査の実施
- 人権擁護、虐待防止への取り組み
- 人材確保、育成対策
- 地域生活拠点整備の推進
- 強度行動障がい支援体制の構築
- 大規模災害対策(BCP)研修会の実施
- 第23回クラシックコンサートの実施
- 第58回全国知的障害福祉関係職員研究大会準備委員会の設置
- 京都知福協50周年記念誌の発刊
- 一般社団法人化に向けての準備会の設置
2017(平成29)年度 京都知的障害者福祉施設協議会事業計画
昨年7月に相模原で起きた事件、事業種別を問わず繰り返される施設内虐待の報道によって、福祉業界はその人材確保において一層深刻な事態を招いています。「人は石垣、人は城、人は堀」福祉の世界に限らずいつの時代にあっても組織は人の力です。この原点に立ち返って、今一度、人を育てる職場風土、支援者にとっての施設・事業所環境のあり方が問われています。現在、社会福祉法人改革において、法人の地域貢献や地域社会にとっての有用性が強く求められています。施設・事業所が所在する地域とダイレクトに繋がっていく中で、本来業務以外の様々なニーズも受け止め、地域の方々にサービスを届ける。身近なところから地域の方たちに法人・事業所に対するメリットを感じてもらい、同時に法人・事業所の取り組みを地域住民に伝え、理解を求める。つまり、双方向の関係性を築いていくことが地域に開かれたこれからの福祉事業のあり方ではないかと思います。こうした地域に根差した取り組みにこれからの福祉を担おうとする若い世代の人たちを積極的に参加させることでこの仕事の魅力・福祉のマインドが伝えられるのではないかと思います。今年度も当協議会の総力をあげて人材の確保と施設事業所内における人材育成の問題に取組みたいと考えています。本会としては、次年度に予定されている福祉サービスの次期報酬改定や制度改正に対応するため日本知福協・近畿知福協と連携を図りながら、最新情報を会員事業所に迅速に提供するとともに、地方会としての具体的な対応を検討し、京都府・市および関係諸団体に積極的な政策提言・意見要望等を発信していきたいと考えています。
2017年度重点項目
- 施設内虐待防止に向けた取り組みと利用者の安全対策
- 大規模災害対策(BPC)の整備
- 強度行動障害者支援モデル事業(京都府)の構築・推進
- 障害者地域生活拠点の推進
- 次期報酬改定と一部制度改正(児童・A型)への対応
- グループホームの安全対策と運営の質向上に向けた取り組み
- 児童分野の課題に対する対応
- 福祉人材確保と育成に向けた研修事業の充実
- 利用者の高齢化対策
■事業の要点
1.全国並びに近畿の組織・役員会・委員会・部会等の取り組み
年間を通じて、総会、役員会、各委員会、各部会等を開催し、事業を推進するとともに、事務局からの情報配信、施設長会議や各種研修会の開催、行政への政策要望書の提出と懇談、行政・関係諸団体との連携などを行い、全国並びに近畿の組織との連携し、障害者総合支援法の施行に係る諸問題の改善や障害者制度の充実に向けた取り組みを進める。
2.組織の強化
- 会員相互の研修・研究交流を図り、密接かつ有機的な連携を図る。
- 会員拡大を図る。
- 事務局体制の充実。(重点項目(6)参照)
3.障害者制度の充実に向けた政策提言と要望活動の取り組み
日本知的障害者福祉協会並びに近畿地区知的障害者施設協会などの関係組織、京都府社会福祉協議会や京都市社会福祉協議会をはじめとする京都府内福祉関係団体、京都府並びに京都市をはじめとする府内市町村との連携し、本会としての意見を集約し、障害者制度の充実に向けた提言や要望活動を京都府、京都市等との意見交換の場を通じて、適切な事業経営と、質の高い福祉サービスの提供を継続することができるよう取り組みを行う。
また、地方自治体への権限移譲が測られる中、市町村によって大きな格差が生じないよう会員相互の連携を図り、京都府並びに市町村への要望を行う。
4.専門性の向上と福祉経営の確立に向けた取り組み
社会福祉法人をとりまく環境が大きく変化し、人権の尊重やサービスの質の向上はもとより、経営組織のガバナンスの強化、コンプライアンスやアカウンタビリティーの徹底、財務基盤の安定化、リスクマネジメントなど、本会会員事業所にも旧来の施設運営から福祉経営へと転換することが求められている。そこで、新たな時代における専門性の向上と福祉経営の確立に向けた次の取り組みを継続して行う。
- 人権擁護と虐待防止に向けた取り組み(重点項目(1))
- 「国連障害者権利条約」をはじめ、「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」「障害者優先調達法」「京都府障害のある人もない人も共にいきいきと暮らしやすい社会づくり条例」など、関連する諸制度について研究・研修を深め、人権擁護意識の向上に努める。
- 人権・倫理委員会、研修委員会を中心に、研究・研修を深め、本会会員事業所職員の人権擁護意識の向上を図り、「虐待防止ひいては「よりよい支援をめざす」取り組みを行う。
- 福祉サービスの充実に向けた取り組み
- 各部会における研究と研修を深める取り組み
- 京都府並びに各市町村との連携による取り組み
- 京都府社会福祉協議会・京都市社会福祉協議会との連携による取り組み
- 京都府福祉・人材研修センター、京都市社会福祉協議会 社会福祉研修・介護実習普及センターとの連携
- 第三者評価を活用し、各々の事業所が専門性の向上と福祉経営の確立に向けた取り組み
- きょうと介護・福祉ジョブネットとの連携を深め、人材確保に向けた取り組み
- 福祉経営の確立に向けた取り組み
事業所を利用する人たちへの支援の質の向上を図るとともに、行政や関係機関、企業等との連携を強化し、障害者雇用の促進、工賃(利用者賃金)の増額、日中活動支援の充実、生活支援の充実等に取り組む
社会福祉法人制度改革や福祉人材の確保、事業所に係るリスクマネジメントなどについての情報収集を行い、新しい福祉経営の在り方について研修等の実施を行う。
5.関係団体との連携
・全国・地区組織関係
- 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会
- 近畿地区知的障害者施設協会
- 一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会
・京都府関係
- 地方分権一括法等に係る福祉施設等の基準検討委員会
- 京都障害者芸術祭実行委員会
- 京都府要配慮者避難支援センター幹事会
・京都市関係
- 京都市障害者施策推進審議会
- 京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議
- 京都子どもネットワーク連絡会議
- 京都市障害者就労支援推進会議
- 京都市障害者地域自立支援協会
- 京都市障害支援区分判定等審査会
- 京都市歯科保健医療サービス困難者普及啓発等事業
・その他
- 京都府社会福祉協議会
- 京都府社会福祉施設協議会
- 京都市社会福祉協議会
- 京都市社会福祉施設連絡協議会
- 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- 京都府発達障害者支援センター連絡協議会
- 障害者権利条約の批准と完全実施をめざす京都実行委員会
- 京都府社会福祉協議会運営適正化委員会
- 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構
- 福祉職場就職フェア実行委員会
- きょうと介護・福祉ジョブネット
2016(平成28)年度 京都知的障害者福祉施設協議会事業計画
平成27年12月社会保障審議会障害者部会に於いて障害者総合支援法施行3年後の見直しについての報告書が示されたことを受け、今年3月1日厚生労働省から障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法案が今国会に上程されました。同時に、社会福祉充実残額(余裕財産)の算出方法や社会福祉法人が取り組まなければならない地域広域活動の基本的な考え方、経営組織の在り方と財務規律の強化、さらには社会福祉施設等退職共済制度(国1/3、都道府県1/3の公費助成)の廃止等を内容とする社会福祉法の一部を改正する法案も上程され、27年度末に可決・成立しました。また、障害者差別解消法が今年4月1日に施行となりましたが、各福祉サービス事業現場に於けるいわゆる「合理的配慮の基準提示やその具体的方法論が確立されておらず、課題が山積しています。まさに障害福祉事業をとりまく変革の時代状況といえます。
本会としては、平成30年度に予定されている障害福祉サービスの次期報酬改定と合わせ、近畿地区知的障害者福祉協会および日本知的障害者福祉協会と連携を図りながら法施行後3年を目途に検討される事項に関する最新情報を会員事業所に迅速に提供すると共に、地方会としての具体的な対応を検討し、新しい制度が障がい者の真の幸福に繋がる恒久的な制度になるよう意見・要望等を発信していかなければならないと考えています。
2016年度重点項目
- 人権擁護と虐待防止に向けた取り組みの実施(役員会、人権・倫理委員会)
- 専門研修の実施
- 危機管理体制の充実に向けた取り組みの実施
- 障害当事者の視点に立った研修事業の実施(公開研修会として実施)
- 本会創立50周年記念史の発刊に向けた取り組み
- 組織体制の充実と事務局の安定的な運営
- 事務局体制の充実
- 京都知的障害児者生活サポート協会との連携
- 弁護士による相談体制の継続・周知
- 本会の法人化に向けた検討
■事業の要点
- 全国並びに近畿の組織・役員会・委員会・部会等の取り組み
年間を通じて、総会、役員会、各委員会、各部会等を開催し、事業を推進するとともに、事務局からの情報配信、施設長会議や各種研修会の開催、行政への政策要望書の提出と懇談、行政・関係諸団体との連携などを行い、全国並びに近畿の組織との連携し、障害者総合支援法の施行に係る諸問題の改善や障害者制度の充実に向けた取り組みを進める。
- 組織の強化
- 会員相互の研修・研究交流を図り、密接かつ有機的な連携を図る。
- 会員拡大を図る。
- 事務局体制の充実。(重点項目6参照)
- 障害者制度の充実に向けた政策提言と要望活動の取り組み
日本知的障害者福祉協会並びに近畿地区知的障害者施設協会などの関係組織、京都府社会福祉協議会や京都市社会福祉協議会をはじめとする京都府内福祉関係団体、京都府並びに京都市をはじめとする府内市町村との連携し、本会としての意見を集約し、障害者制度の充実に向けた提言や要望活動を京都府、京都市等との意見交換の場を通じて、適切な事業経営と、質の高い福祉サービスの提供を継続することができるよう取り組みを行う。
また、地方自治体への権限移譲が測られる中、市町村によって大きな格差が生じないよう会員相互の連携を図り、京都府並びに市町村への要望を行う。 - 専門性の向上と福祉経営の確立に向けた取り組み
社会福祉法人をとりまく環境が大きく変化し、人権の尊重やサービスの質の向上はもとより、経営組織のガバナンスの強化、コンプライアンスやアカウンタビリティーの徹底、財務基盤の安定化、リスクマネジメントなど、本会会員事業所にも旧来の施設運営から福祉経営へと転換することが求められている。そこで、新たな時代における専門性の向上と福祉経営の確立に向けた次の取り組みを継続して行う。
- 人権擁護と虐待防止に向けた取り組み(重点項目(1))
- 「国連障害者権利条約」をはじめ、「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」「障害者優先調達法」「京都府障害のある人もない人も共にいきいきと暮らしやすい社会づくり条例」など、関連する諸制度について研究・研修を深め、人権擁護意識の向上に努める。
- 人権・倫理委員会、研修委員会を中心に、研究・研修を深め、本会会員事業所職員の人権擁護意識の向上を図り、「虐待防止ひいては「よりよい支援をめざす」取り組みを行う。
- 福祉サービスの充実に向けた取り組み
- 各部会における研究と研修を深める取り組み
- 京都府並びに各市町村との連携による取り組み
- 京都府社会福祉協議会・京都市社会福祉協議会との連携による取り組み
- 京都府福祉・人材研修センター、京都市社会福祉協議会 社会福祉研修・介護実習普及センターとの連携
- 第三者評価を活用し、各々の事業所が専門性の向上と福祉経営の確立に向けた取り組み
- きょうと介護・福祉ジョブネットとの連携を深め、人材確保に向けた取り組み
- 福祉経営の確立に向けた取り組み
事業所を利用する人たちへの支援の質の向上を図るとともに、行政や関係機関、企業等との連携を強化し、障害者雇用の促進、工賃(利用者賃金)の増額、日中活動支援の充実、生活支援の充実等に取り組む
社会福祉法人制度改革や福祉人材の確保、事業所に係るリスクマネジメントなどについての情報収集を行い、新しい福祉経営の在り方について研修等の実施を行う。
- 関係団体との連携
- 全国・地区組織関係
- 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会
- 近畿地区知的障害者施設協会
- 一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会
- 京都府関係
- 地方分権一括法等に係る福祉施設等の基準検討委員会
- 京都障害者芸術祭実行委員会
- 京都府要配慮者避難支援センター幹事会
- 京都市関係
- 京都市障害者施策推進審議会
- 京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議
- 京都子どもネットワーク連絡会議
- 京都市障害者就労支援推進会議
- 京都市障害者地域自立支援協会
- 京都市障害支援区分判定等審査会
- 京都市歯科保健医療サービス困難者普及啓発等事業
- その他
- 京都府社会福祉協議会
- 京都府社会福祉施設協議会
- 京都市社会福祉協議会
- 京都市社会福祉施設連絡協議会
- 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- 京都府発達障害者支援センター連絡協議会
- 障害者権利条約の批准と完全実施をめざす京都実行委員会
- 京都府社会福祉協議会運営適正化委員会
- 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構
- 福祉職場就職フェア実行委員会
- きょうと介護・福祉ジョブネット
2015(平成27)年度 京都知的障害者福祉施設協議会事業計画
2015年度を迎え、各事業所とも障害福祉サービス等報酬単価改定等に伴う、運営の見直し、各種事務手続き等に追われた年度当初になったのではないでしょうか。
今年度、2016年4月を目途とした障害者総合支援法の施行後3年を目途とした見直しの一環として障害者総合支援法の見直しに向けた審議を厚生労働省は始めています。一方、その審議に合わせるかのように財務省は社会保障関係費の一環で障害福祉の見直しの論点を示しました。また、今国会に提出された「社会福祉法等の一部を改正する法案への対応などもあり、これらの動きは社会福祉法人の運営や障害福祉に直接かかわってくる課題であり、注目をしていかなければなりません。
本会は、引き続き障害者総合支援法の諸課題への対応に向けた取り組みを行うとともに、2014年度に残した課題を含め、下記の重点項目を継続して実施し、新たな時代にふさわしい組織体へと更なる自己変革を進め、障害のある人たちの人権を擁護し、自立と社会参加の促進に寄与すべく2015年度事業計画を策定するものとします。
2015年度重点項目
- 人権擁護と虐待防止に向けた取り組みの実施(役員会、人権・倫理委員会)
- 支援スタッフ委員会の創設
- 2015年度近畿地区職員研修の実施(研修委員会・支援スタッフ委員会)
- 障害当事者の視点に立った研修事業の実施(研修委員会・京都障害児者生活サポート協会との共催)
- 本会創立50周年記念事業の検討 → 実行委員会設立
- クラシックコンサート再開に向けた準備【京都親の会協議会・京都障害児者サポート協会との共催】
- 組織体制の充実と事務局の安定的な運営についての検討
- 各種規程の見直しと整備 → 検討委員会設立【役員等選任規程の見直し・個人情報管理規程・旅費規程等の整備】
- 事務局体制の充実
- 京都知的障害児者生活サポート協会との連携
- 弁護士による相談体制の強化の検討(顧問弁護士との委託契約の検討)
- 本会の法人化に向けた検討
Ⅰ.事業の要点
- 全国並びに近畿の組織・役員会・委員会・部会等の取り組み
年間を通じて、総会、役員会、各委員会、各部会等を開催し、事業を推進するとともに、事務局からの情報配信、施設長会議や各種研修会の開催、行政への政策要望書の提出と懇談、行政・関係諸団体との連携などを行い、全国並びに近畿の組織との連携し、障害者総合支援法の施行に係る諸問題の改善や障害者制度の充実に向けた取り組みを進める。
- 組織の強化
- 会員相互の研修・研究交流を図り、密接かつ有機的な連携を図る。
- 会員拡大を図る。
- 事務局体制の充実を図るための方策の検討。(重点項目(7)参照)
- 障害者制度の充実に向けた政策提言と要望活動の取り組み
日本知的障害者福祉協会並びに近畿地区知的障害者施設協会などの関係組織、京都府社会福祉協議会や京都市社会福祉協議会をはじめとする京都府内福祉関係団体、京都府並びに京都市をはじめとする府内市町村との連携し、本会としての意見を集約し、障害者制度の充実に向けた提言や要望活動を京都府、京都市等との意見交換の場を通じて、適切な事業経営と、質の高い福祉サービスの提供を継続することができるよう取り組みを行う。
また、地方自治体への権限移譲が測られる中、市町村によって大きな格差が生じないよう会員相互の連携を図り、京都府並びに市町村への要望を行う。 - 専門性の向上と福祉経営の確立に向けた取り組み
社会福祉法人をとりまく環境が大きく変化し、人権の尊重やサービスの質の向上はもとより、経営組織のガバナンスの強化、コンプライアンスやアカウンタビリティーの徹底、財務基盤の安定化、リスクマネジメントなど、本会会員事業所にも旧来の施設運営から福祉経営へと転換することが求められている。そこで、新たな時代における専門性の向上と福祉経営の確立に向けた次の取り組みを継続して行う。
- 人権擁護と虐待防止に向けた取り組み(重点項目(1))
- 「国連障害者権利条約」をはじめ、「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」「障害者優先調達法」「京都府障害のある人もない人も共にいきいきと暮らしやすい社会づくり条例」など、関連する諸制度について研究・研修を深め、人権擁護意識の向上に努める。
- 人権・倫理委員会、研修委員会を中心に、研究・研修を深め、本会会員事業所職員の人権擁護意識の向上を図り、「虐待防止
ひいては「よりよい支援をめざす」取り組みを行う。 - 福祉サービスの充実に向けた取り組み
- 各部会における研究と研修を深める取り組み
- 京都府並びに各市町村との連携による取り組み
- 京都府社会福祉協議会・京都市社会福祉協議会との連携による取り組み
- 京都府福祉・人材研修センター、京都市社会福祉協議会 社会福祉研修・介護実習普及センターとの連携
- 第三者評価を活用し、各々の事業所が専門性の向上と福祉経営の確立に向けた取り組み
- きょうと介護・福祉ジョブネットとの連携を深め、人材確保に向けた取り組み
- 福祉経営の確立に向けた取り組み
事業所を利用する人たちへの支援の質の向上を図るとともに、行政や関係機関、企業等との連携を強化し、障害者雇用の促進、工賃(利用者賃金)の増額、日中活動支援の充実、生活支援の充実等に取り組む
社会福祉法人制度改革や福祉人材の確保、事業所に係るリスクマネジメントなどについての情 報収集を行い、新しい福祉経営の在り方について研修等の実施を行うとともに、専門家(弁護士)による顧問契約の検討を行う。
- 関係団体との連携
- 全国・地区組織関係
- 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会
- 近畿地区知的障害者施設協会
- 一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会
- 京都府関係
- 地方分権一括法等に係る福祉施設等の基準検討委員会
- 京都障害者芸術祭実行委員会
- 京都府要配慮者避難支援センター幹事会
- 京都市関係
- 京都市障害者施策推進審議会
- 京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議
- 京都子どもネットワーク連絡会議
- 京都市障害者就労支援推進会議
- 京都市障害者地域自立支援協会
- 京都市障害支援区分判定等審査会
- 京都市歯科保健医療サービス困難者普及啓発等事業
- その他
- 京都府社会福祉協議会
- 京都府社会福祉施設協議会
- 京都市社会福祉協議会
- 京都市社会福祉施設連絡協議会
- 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- 京都府発達障害者支援センター連絡協議会
- 障害者権利条約の批准と完全実施をめざす京都実行委員会
- 京都府社会福祉協議会運営適正化委員会
- 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構
- 福祉職場就職フェア実行委員会
- きょうと介護・福祉ジョブネット
2014(平成26)年度 京都知的障害者福祉施設協議会事業計画
2014年度を迎え、障害者総合支援法の施行に係わる検討課題のうち、本年4月から施行される「障害支援区分」「重度訪問介護の拡大」「ケアホームとグループホームの一元化」等が実施される。しかし、現場で実際に支援に係わっているものとしては、いくつかの課題や矛盾を抱えながらの船出となった。
今後、2016年を目途とした見直しや、附帯決議で指摘された「小規模入所施設」の検討、市町村及び都道府県において第4期障害福祉計画(計画期間:2015~2017年度)の検討などが行われるが、このことにも注目が必要である。
また、政府の「規制改革会議」厚生労働省の「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」等においては、社会福祉法人の適正な運営の確保、営利法人とのイコールフィッティング等についての論議が行われており、社会福祉法人の「あるべき姿」を求めている。公益法人として社会の期待に応えるために、サービスの質の向上、事業の透明性の確保、地域福祉にいかに貢献し、地域福祉の拠点となることが求められている。
本会は、引き続き障害者総合支援法の諸課題への対応に向けた取り組みを行うとともに、2013年度重点項目を継続して実施し、新たな時代にふさわしい組織体へと更なる自己変革を進め、障害のある人たちの人権を擁護し、自立と社会参加の促進に寄与すべく2014年度事業計画を策定するものとする。
2014年度重点項目
- 人権擁護と虐待防止に向けた取り組みの実施
- 障害当事者の視点に立った研修事業の実施
- 組織体制の充実と事務局の安定的な運営についての検討
- 支援スタッフ委員会(仮称)の創設の検討と試行
- 2014年度近畿地区施設長会議の開催(12月9日・10日開催予定)
- 2015年度近畿地区職員研修の準備
- 本会創立50周年記念事業の検討
- 本会の法人化に向けた検討
Ⅰ.事業の要点
- 役員会・委員会・部会等の取り組み
年間を通じて、総会、役員会、各委員会、各部会等を開催し、事業を推進するとともに、事務局からの情報配信、施設長会議や各種研修会の開催、行政への政策要望書の提出と懇談、行政・関係諸団体との連携などを行い、全国並びに近畿の組織との連携し、障害者総合支援法の施行に係る諸問題の改善や障害者制度の充実に向けた取り組みを進める。
- 組織の強化
- 会員相互の研修・研究交流を図り、密接かつ有機的な連携を図る。
- 支援スタッフ委員会(仮称)の創設の検討と試行。
※支援スタッフ委員会(仮称):支援に携わるスタッフの視点から、利用者支援の向上などに向けた取り組みを行う。たとえば「若手スタッフ育成研修実行委員会」「現場スタッフ交流事業」などの実施を検討・試行する。 - 会員拡大を図る。
- 事務局体制の充実を図るための方策の検討。
- 障害者制度の充実に向けた政策提言と要望活動の取り組み
日本知的障害者福祉協会並びに近畿地区知的障害者施設協会などの関係組織、京都府社会福祉協議会や京都市社会福祉協議会をはじめとする京都府内福祉関係団体、京都府並びに京都市をはじめとする府内市町村との連携し、本会としての意見を集約し、障害者制度の充実に向けた提言や要望活動を京都府、京都市等との意見交換の場を通じて、適切な事業経営と、質の高い福祉サービスの提供を継続することができるよう取り組みを行う。
また、地方自治体への権限移譲が測られる中、市町村によって大きな格差が生じないよう会員相互の連携を図り、京都府並びに市町村への要望を行う。主な視点
- 障害者総合支援法における検討課題への対応と要望
- 障害者の就労支援その他のサービスの在り方
- 障害支援区分の認定を含めた支援決定の在り方
- 高齢障害者に対する支援の在り方
- 障害児支援の在り方についての検討と要望
- 社会福祉法人の在り方の見直しへの対応
- 大規模災害等への防備について
- 専門性の向上と福祉経営の確立に向けた取り組み
社会福祉法人をとりまく環境が大きく変化し、人権の尊重やサービスの質の向上はもとより、コンプライアンスやアカウンタビリティーの徹底、財務基盤の安定化や組織統治の確立などにより、本会会員事業所にも旧来の施設運営から福祉経営へと転換することが求められている。そこで、新たな時代における専門性の向上と福祉経営の確立に向けた次の取り組みを継続して行う。
- 人権擁護と虐待防止に向けた取り組み
- 新たな障害者制度の基盤となる「国連障害者権利条約」をはじめ、関連する諸制度について研究・研修を深め、人権擁護意識の向上に努める。
- 京都府が2008年に実施した「障害者施設における身体拘束に関する調査」について、その後の状況を、2013年度政策委員会を中心に追加調査を実施した。その結果を踏まえ「障害のある人の尊厳を重んじた支援」について取り組みを深める。
- 人権・倫理委員会、研修委員会を中心に、研究・研修を深め、本会会員事業所職員の人権擁護意識の向上を図り、「虐待防止」ひいては「よりよい支援をめざす」取り組みを行う。
- 福祉サービスの充実に向けた取り組み
- 各部会における研究と研修を深める取り組み
- 京都府並びに各市町村との連携による取り組み
- 京都府社会福祉協議会・京都市社会福祉協議会との連携による取り組み
- 京都府福祉・人材研修センター、京都市社会福祉協議会 社会福祉研修・介護実習・普及センターとの連携
- 第三者評価を活用し、各々の事業所が専門性の向上と福祉経営の確立に向けた取り組みを行う
- きょうと介護・福祉ジョブネットとの連携を深め、人材確保に向けた取り組み
事業所を利用する人たちへの支援の質の向上を図るとともに、行政や関係機関、企業等との連携を強化し、障害者雇用の促進、工賃(利用者賃金)の増額、日中活動支援の充実、生活支援の充実等に取り組む
- 関係団体との連携
- 全国・地区組織関係
- 日本知的障害者福祉協会
- 近畿地区知的障害者施設協会
- 京都府関係
- 地方分権一括法等に係る福祉施設等の基準検討委員会
- 京都障害者芸術祭実行委員会
- 京都府要配慮者避難支援センター幹事会
- 京都市関係
- 京都市障害者施策推進審議会
- 京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議
- 京都子どもネットワーク連絡会議
- 京都市障害者就労支援推進会議
- 京都市障害者地域自立支援協会
- 京都市障害支援区分判定等審査会
- 京都市歯科保健医療サービス困難者普及啓発等事業
- その他
- 京都府社会福祉施設協議会 ※京都府社会福祉協議会
- 京都市社会福祉施設連絡協議会 ※京都市社会福祉協議会
- 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- 京都府発達障害者支援センター連絡協議会
- 障害者権利条約の批准と完全実施をめざす京都実行委員会
- 京都府社会福祉協議会運営適正化委員会
- 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構
- 福祉職場就職フェア実行委員会
- きょうと介護・福祉ジョブネット
(主な関係団体 委員・役員等の一覧)